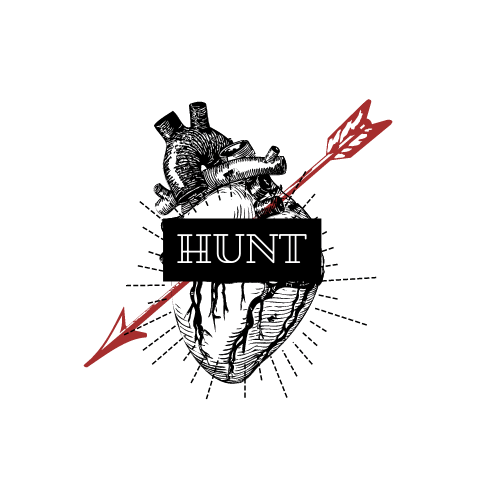9. 或る夜のこと
Caption
人間に買われた獣人の少女と、彼女を殺した幼いルーク・ハントの話。
成分表:ネームレス獣人女主夢 | 人身売買・児童虐待 | 死ネタ
私は獣人を殺したことがある。あれはまだほんの子供の、美しい羽根を持つ獣人だった。
人間、獣人、人魚に妖精。種族は違えど生きとし生けるものはみな美しく、その命は平等に尊重されるべきものだ。異種族間での戦争が頻発していた時代と比べれば、種族間の争いは大幅に減り、国際的な法の整備や倫理観のすりあわせが行われるようになってきた。
とはいえ誰もが法や倫理を守るわけではないし、そもそも違法なものが全て裁かれるわけでもない。
私がプライマリースクールに入る前の年。父親の仕事相手が主催するパーティに招かれたときのこと。主催者の自宅で行われる、立食形式の小規模なパーティ。そうは言っても仕事の延長線上のようなものなので、会場にいるのは「大人」と「大人に顔見せしておきたい年齢の子供」ばかり。もちろん退屈で仕方がなかったが、皴ひとつない窮屈な服に身を包むときにどう振舞うべきかを理解しているような子供だった。壁際の椅子に腰かけ、足をぶらぶらと揺らしながら、母にとってもらった料理を静かに食べる姿を見て可哀想に思ったのだろう。
「いいものを見せてあげよう」
主催者の男がそう声をかけてきたのは、私が器の中で溶け始めたデザートのアイスクリームをスプーンで突っついていたときのことだった。
私と数人の子供たちを連れた彼は、明るい大広間を出て長い廊下を何度か曲がると、突き当たりにある部屋の前で足を止めた。
「大きな声を出してはいけないよ。アレが怖がってしまうから」
そう言いながら男がドアを開けた瞬間、薄暗い部屋の中でなにか身動ぎをするのがわかった。
広い部屋の中心に置かれた、巨大な鳥籠と、その中心で蹲るなにか。事前に忠告されたように大きな音を立てないよう気をつけながらおそるおそる部屋の中に足を踏み入れたそのとき。突然、目の前いっぱいに鮮やかな色彩が広がった。
カーテンの隙間から差し込むわずかな月明かりを浴びて、キラキラと色を変えて輝くもの。一枚の絵画のように見えるそれが、大きく広げられた翼であることに気がついたのは、その中心で爛々と光る赤い双眸に弾けるような殺気が閃いたからだ。
「ウ……」
周りの子供たちが息を呑む音が聞こえた。その翼の美しさのせいではない。視線だけで人を殺せそうなほどの殺気を放つ目の前の生き物から聞こえた声が、私たちとさほど変わらぬ子供のものだったからだ。
「触れてはいけないよ。人間とは違うんだ。指を食いちぎられてしまうかもしれない」
「この子は……」
「この間買いつけた獣人だよ。種類はいま調べているところだが、美しいだろう」
獣人を売買し、飼育するのは違法だ。五歳の私でも知っていたその事実を、周りの子供たちが知らぬはずはなかった。しかし「大人の世界に顔見せをする」ために連れて来られた彼らが、パーティの主催者である男の前でそれを口に出すことはない。彼らは愛想笑いをするには少し幼く、なにも知らずに賞賛するには大人すぎた。それに、目の前で必死にこちらを威嚇してみせる小さな獣人は、見て見ぬふりをするにはあまりにも美しすぎたのだ。
「……名前は?」
「名前? まだつけていないが……折角だから、坊やがつけてやってくれるかい?」
どうしてそんなことを聞いたのか、よく覚えていない。しかしきっと目の前の獣人にも名前はあるのだろうと思ったし、それをわかったうえでそんな提案をしてくる男に言いようのない嫌悪感を抱いたことはハッキリと覚えている。
そのとき男を呼びにきた人間が部屋の扉をノックする音が聞こえ、私たちはみんなそろって大広間へ戻ることになった。しかし美しい調度品が並ぶ廊下を歩いている間も、両親とともに宛がわれた客室に移動している間も、私の頭の中はあの美しい翼を持つ獣人のことでいっぱいだった。
宴が終わり、帰路に就こうとしていた私たちを引き留めたのは、主催者の男だった。まだ幼い坊ちゃんを連れて夜道を行くのは大変でしょう。まだ話したいこともあります。部屋だけはたくさんあるのでよければ泊っていってほしい。詳しくは覚えていないが、おそらくそんなところだろう。そしてそんな仕事相手の「親切」を無下にすることができるはずもなく、私たちは男の屋敷で一泊することになった。
子供は寝る時間だという言葉に従い大人しくベッドに身を横たえた私は、部屋から両親の足音が遠ざかっていくのを確認したあと素早く身体を起こした。残念ながら、その日私が身につけていたのは履きなれたブーツではなくよそ行きの革靴。足音を殺しにくく、機動力も低いそれを履くぐらいならと、裸足のまま客室を飛び出した。
飲み直しているのだろう、大人たちの談笑の声が聞こえる部屋の外を静かに通り過ぎ、まっすぐ目的の部屋へと向かう。一度連れられただけだったが、部屋の場所はハッキリと覚えていた。
幸運にも、部屋の扉に鍵はかかっていなかった。近くに誰もいないことを確認してから、息を殺して扉を開ける。
「……!」
「シッ……騒がないで。今、そこから出してあげる」
暗闇の中で、赤い瞳が探るようにじっと私を見つめる。その美しい緋色と視線をあわせたまま、私はゆっくりと鳥籠の側に近寄った。
鳥籠に鍵がついていないことは、最初に足を踏み入れたときに確認していた。指先にぐっと力をいれて、しっかりとはめ込まれた金属製の閂を動かせば、檻の中の獣人がびくりと肩を震わせる。
「おいで」
「……ッ」
「あの窓から出られるから」
なるべく刺激を与えないよう、ゆっくりと窓のある方角を指さす。消灯前でまだ戸締りに来ていないのか、そこにはちょうど子供一人が通り抜けられそうな隙間が空いていた。
戸惑いと疑い、そして少しの恐怖が混ざった視線。しばらく無言で私を睨みつけていた獣人は、決意を固めたようにゴクリと唾を飲みこむと、姿勢を低くしたまま鳥籠の中から這い出てきた。
伸びをするようにばさりと広げられた、美しい翼。ブラックオパールのように角度によって色を変えるその両翼に見入っていると、静かな部屋の中に小さな声が響いた。
「おまえ、どうしてこんなことをする?」
少しカサついた、少女の声。咄嗟になんと返せばいいのかわからず口ごもった私を、彼女は表情を変えずにじっと見つめた。
「……キミにはこんな場所、似合わないから」
獣人を閉じこめるのが悪いことだからとか、あの男が気に食わないとか、理由はいろいろあったように思う。それでも私の頭に最初に浮かんだのは、彼女の翼の美しさだった。この美しい翼は、大空を自由に飛び回るためにあるもので、薄暗い鳥籠の中で飼い殺しにされるためのものではない。彼女は自由であるべきだと、ただそう思った。
「さあ、行って」
彼女がその美しい翼をばさりと動かすと、室内で小さな風が巻き起こる。小さな竜巻のようなそれに目を細めた私の前で、彼女は冷たい床を蹴って飛び立った。
「…………ありがと」
窓枠に足をかけ、部屋から飛び出す直前に、彼女は相変わらず表情を変えずに私を見下ろしそう言った。
月明かりの下、美しい翼を広げて飛び去る一人の少女。目の奥に焼きついたその姿に高揚したまま、私は静かに客室へと戻ってベッドに飛び込んだ。
屋敷の前で死体となった彼女が発見されたのは、その翌朝のことだった。
この作品を共有

👏waveboxで拍手 💌フォームで感想
読んだよ!報告、感想とても嬉しいです!ありがとうございます!